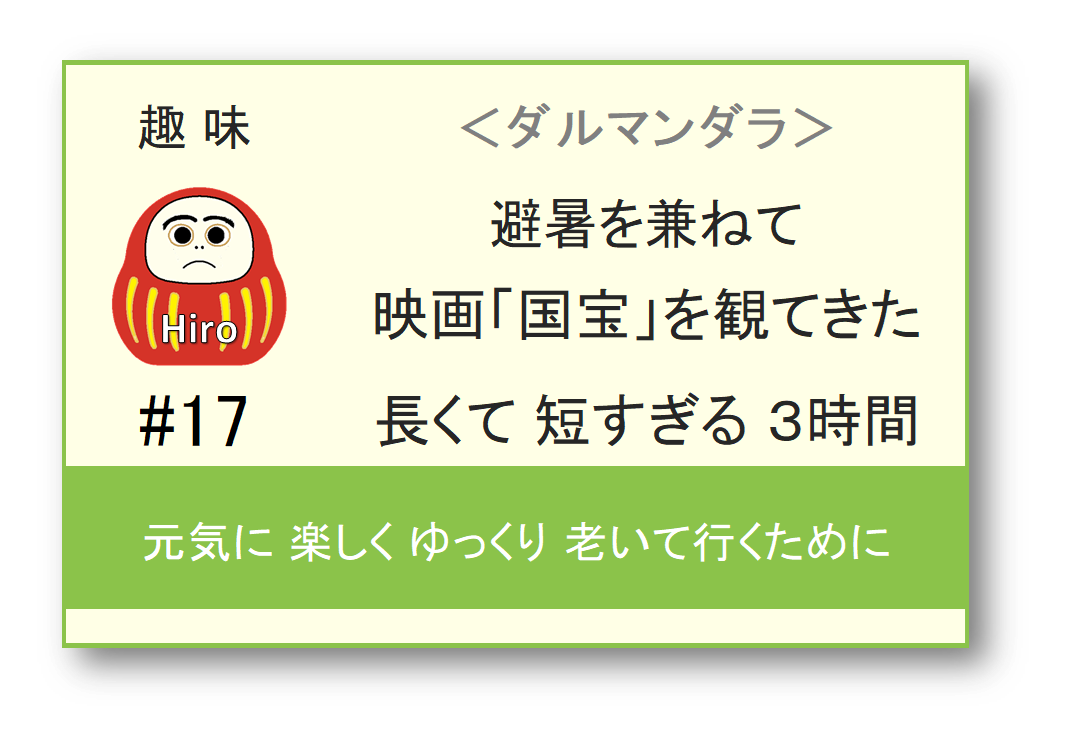お盆が過ぎたが、まだまだ猛暑が続くので、涼を求め、映画館へ行くことにした。
期待半分・・・
夏休み中とあって「鬼滅の刃」や「クレヨンしんちゃん」など アニメが多い。
その中に、歌舞伎の世界を題材にした「国宝」という映画があった。
YouTubeで調べてみると「感動した」「間違いなく名作だ」と 高評価のレビューが並んでいる。
上映時間は 175分。
長いが、おもしろければ充実した時間を過ごせる。
でなければ、苦痛な時間になる。
歌舞伎に関する 知識も興味もないが、シニア割引で1300円。
思い切って出かけてみた。
あらすじ
任侠の家に生まれた少年・喜久雄(吉沢亮)。
父を抗争で失い、行き場をなくした彼は、上方歌舞伎の名門・花井半二郎(渡辺謙)に引き取られる。
そこで出会ったのは、生まれながらに将来を約束された御曹司・俊介(横浜流星)。
正反対の血筋、異なる才能。
やがて二人は友情で結ばれ、同時に互いを刺激し合うライバルとなっていく。
が、栄光と挫折、愛と別れを経て、運命の歯車は 次第に大きく狂い始める──。
物語は、喜久雄の50年にわたる激動の人生と、
歌舞伎という 芸の世界に身を捧げた男たちの 壮大なドラマを描き出していく。
消化不良
見終わった後の感想としては、特に心を動かされることはなかった。
つまらなくはないが、おもしろくもない。
本当は感動したかった。
レビューのように「名作だった」と言いたかった。
しかし、なぜか心が動かない。
消化不良のまま、映画館を後にした。
なぜ心が動かなかったのか
理由はいくつか考えられる。
歌舞伎を知らない自分の側の問題
演舞の映像が長く続くが、私にはその出来栄えがわからない。
喜久雄と俊介の技能の違いもわからない。
「女方」を演じる姿も、どうしても「男」にしか見えない。
顔のアップも写し出されるが、美しいとは思えない・・・・。
人間国宝となった喜久雄の演舞も、そのすごさを感じる事はできなかった。
そもそも プロではない役者の演舞を 長々と映す必要があるのだろうか、
とさえ 思ってしまう。
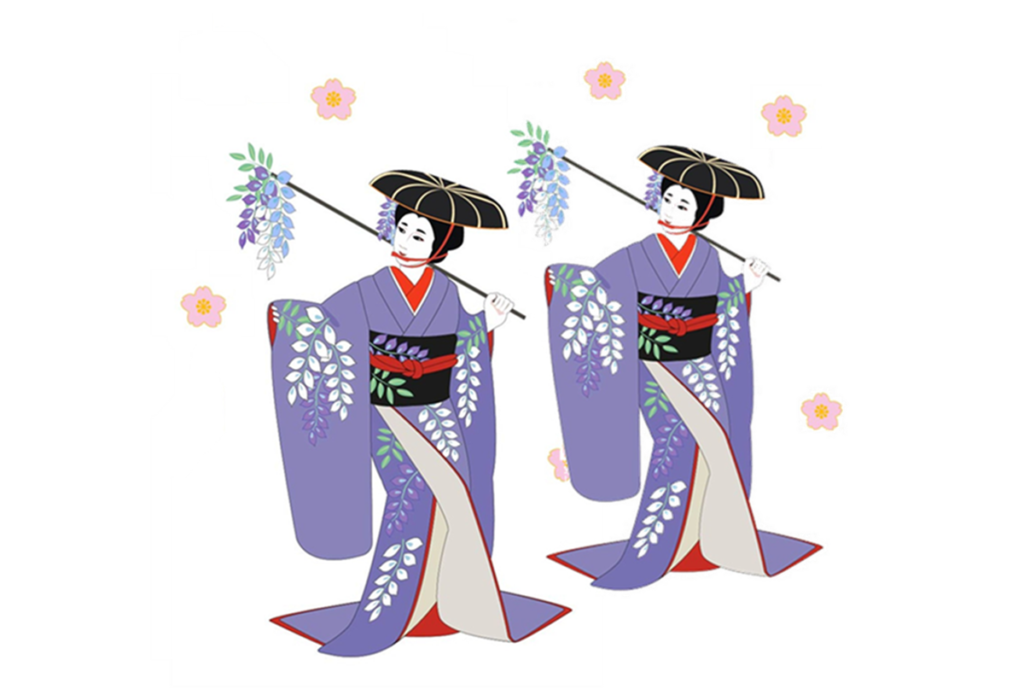
私には、この映画を鑑賞する能力が 不足しているのかもしれない。
そしてもうひとつは、作品そのものの描き方
喜久雄 と 俊介の 友情やライバル関係、彼らに関わる 女性との心の動きが、あまりにも簡単に描かれている。
人の関わりは 本来もっと複雑で、濃密であるはずなのに、
説明的な ストーリーだけが 展開されていくように感じられた。
「この場面は 感動させようとしているんだろうな」
「この台詞は 後の伏線かも」などと、
冷静な目で観てしまう。
こうなると 心は動かない。
長くて、短すぎた3時間
3時間は長かった。
だが同時に、喜久雄の 50年を描くには 短すぎた とも思う。
人と人との関わりを丁寧に描くには、もっと時間が必要だ。
芸を極めるための、努力とか苦悩を描くにも、もっと時間が必要だ。
もし連続ドラマで作られ、ひとつひとつの場面を じっくり表現できたなら──。
そして 今回の映画が、そのドラマの ダイジェスト版だとすれば──。
そう 考えてみた。
ダイジェスト版だと思えば
一般的に、ダイジェスト版は、省略されたが故の わかりずらさや、物足りなさ を感じてしまう。
この感覚が、今回の映画を観た 私の印象としては、一番しっくりくる。
決して この映画を批判するつもりはない。
むしろ、多くの高評価のレビューをみると、自分の感性に 自信がなくなる。
なので、映画鑑賞能力に自信のある方には、楽しめる映画だと思う。
映画をきっかけに浮かんだ素朴な疑問
今回の映画で 歌舞伎の演舞を観ながら、ずっと気になっていたことがある。
それは「女方(おんながた)は なぜ男性が演じるのか?」ということだ。
女性が演じた方が 自然で美しいのではないか──そんな素朴な疑問だった。
少し調べてみると、江戸時代には 女性が舞台に立つことは風紀を乱すとされ 禁じられたため、
男性が女性を演じる「女方」という役柄が生まれたらしい。
そういえば、映画の冒頭にもそんな説明があった気がする。
そして、男性が演じるからこそ作り上げられる「理想化された女性像」があり、
それは現実の女性の所作とは違う「芸」としての美しさ なのだそうだ。
しかし「なるほど」とは 素直に理解できない。
女性による歌舞伎
正直に言えば、私はやはり 本物の女性の 美しい演舞を観てみたい。
現代であれば、女性が歌舞伎に参加しても よいのではないか。
男女どちらが演じるかで 表現の幅が広がり、歌舞伎はさらに面白くなるのではないかと、
素人ながら感じてしまう。
ここで思い出すのが 宝塚歌劇団だ。
宝塚は女性だけで構成され、男性役も 女性が演じる。
もしかすると、女性同士で演じることで、
恋愛や接触の場面における「なまめかしさ」が薄れ、確かに 物語に集中しやすくなる効果が あるのかもしれない。
そう考えると、歌舞伎に「女方」が存在する理由にも、ある程度 納得できる。
歌舞伎の伝統
歌舞伎は国の重要無形文化財に指定され、人間国宝も多く輩出している。
そのためか、どうしても「敷居が高い」という印象がある。
伝統を維持するために、役者や関係者は 日々研鑽を積み、厳しいプレッシャーの中で 芸を守り続けているのだろう。
時々 歌舞伎界のスキャンダルが 話題になるのも、そうした閉ざされた環境のストレスが 一因なのかもしれない。
もともと、歌舞伎は 庶民の娯楽として始まったものだと思う。
伝統を守ることは大切だが、同時に「気軽に楽しめる娯楽」としての魅力を残すことも 重要だろう。
歌舞伎の存在意義を改めて問い直し、伝統を守りながら新しい挑戦を続けること。
血筋や家柄にこだわらず、才能ある人材に門戸を広げること。
そうした取り組みを怠れば、歌舞伎はやがて衰退してしまうのではないか。
もちろん、素人が口にするまでもなく、歌舞伎界では すでに様々な改革が進められているようだ。
変わらない魅力もある。
変化しなければ 開けない未来もある。
存続するための 伝統と挑戦。
歌舞伎に限らず、伝統芸能は、その岐路に立っているのかもしれない。
最後に
映画を観て、少なからず歌舞伎に興味がわいてきた。
今のままでは、この映画を鑑賞する感性は身に付きそうもない。
歌舞伎に限らず、伝統芸能に接する機会も つくってみようかと思う。
<他の映画レビュー>
「ローマの休日」レビュー を 読む
フェリーニの「道」 レビュー を 読む
「東京物語」 レビュー を 読む